フィンランドには「SISU(シス)」という言葉があります。
これは日本人にはあまりなじみのない概念ですが、「逆境に立ち向かい、最後まで諦めない強さ」を意味します。
日本で言うなら「武士道」に近い精神かもしれません。
どんな困難にぶつかっても逃げずに越えていく、その姿勢が人を成長させるのです。
SISUと武士道の共通点
SISUは、ただの根性論や我慢ではありません。
心が折れそうになっても冷静さと勇気を失わず、希望を手放さない精神です。
それは「武士道」とも響き合います。
武士道は忠義や勇気、名誉を重んじ、自らを律しながら困難を超えていく精神。
どちらにも共通しているのは「壁を避けるのではなく、壁を越えることで人は磨かれる」という信念です。
フィンランド社会の変化
しかし、現代のフィンランドでは社会保障や教育制度があまりに充実したために、SISU精神が揺らいでいるとも言われています。
安心安全は守られる。困ったら国が助けてくれる。
それは素晴らしい仕組みである一方で、「自分の力で壁を越える」経験を奪ってしまうのです。
これはまさに「過保護」と同じ構造です。
守られすぎることで、人は挑戦する力を失ってしまうのです。
過保護とSISUの違い
過保護は「苦しむ姿を見たくない」という親の気持ちから生まれます。
だから、つい手を差し伸べすぎてしまう。
一方、SISUを信じる接し方は違います。
「倒れても立ち上がれる力がある」と信じ、あえて突き放す。
守ることと突き放すこと、その両方が必要なのです。
私自身のケース
私にも、息子との間で大きな決断を迫られた瞬間がありました。
特殊任務の強化訓練に挑んだ息子は、精神をすり減らし「もう辞めたい」と懇願しました。
ノイローゼのようになり、本当は別の道を歩みたいと口にする彼を見て、母親として胸が締めつけられました。
正直に言えば、安心させたい、辛い顔を笑顔に変えたい、過保護になるのは簡単でした。
でも、その瞬間に思ったのです。
「ここで壁を越えなければ、この子は一生、前へ進めない」
私は嫌われても恨まれてもいい、と覚悟して突き放しました。
その後、息子は自らの力で強化訓練をやり遂げました。
そして私は、やり切った者だけが持つ「男の顔」を見たのです。
その顔は、母親の手では不可能な領域に踏み込んだ者だけの強さがありました。
親のSISUとは
この経験を通して学んだことがあります。
それは、子どもを信じて突き放すことこそ、親にとってのSISUだということです。
「厳しいだけ」は虐待です。
そこには必ず、親子の信頼関係が前提になければなりません。
壁を越えても越えても、人生にはまた次の壁が現れます。
それは子どもだけでなく、親である私自身も同じです。
だから私は、子どもたちに「心配」を抱くのではなく、
「壁の乗り越え方」を伝える人でありたい。
結び
SISUとは「困難を避けず、信念をもって超える精神」です。
それは過保護ではなく、信じて見守る勇気。
私は息子たちに願います。
成長をやめずに歩み続けてほしい。
そしてそのために、私自身もまた歩みを止めることはありません。
親の背中で示すことこそ、最高のアドバイスだからです。
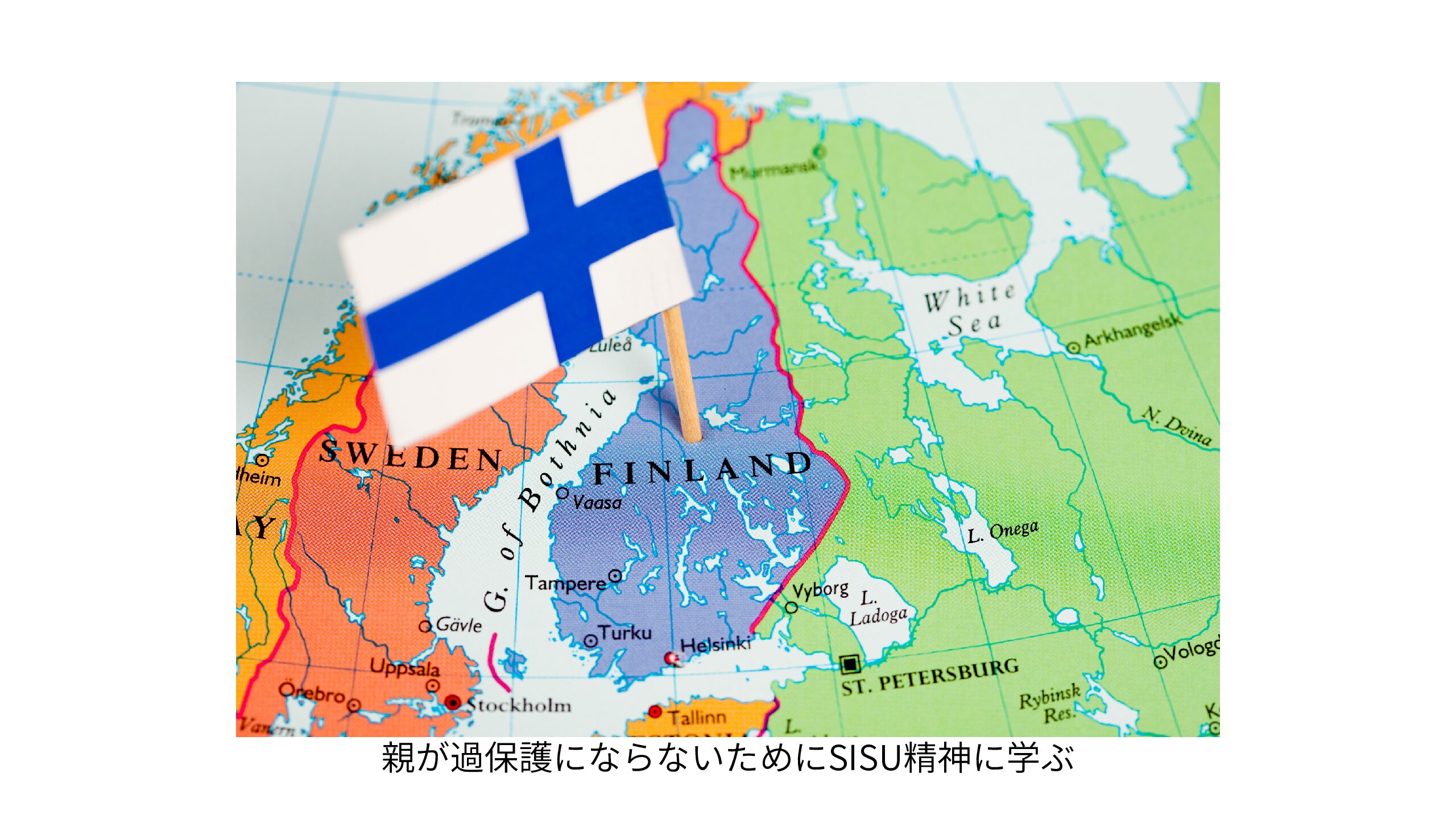


コメント