第1章:子育ての終わりって、いつなの?
ある日、家の整理をしていた私は、息子の昔のゲームや本を
「もう要らないだろう」と思い、何気なく処分しました。
すると、「え、それ捨てたの?勝手にやめてよ!弁償して!」と、息子に強い口調で怒られました。
思わず私はこう返しました。
「そんなに大事なら、最初から言っておいてよ」
でも息子は、もっと怒りを強めてこう言ったのです。
「当たり前だろ!言わなくてもわかるだろ!」
このやり取りは、私の中で大きな気づきをくれました。
子どもが小さい頃は、
親がすべてを管理し、決めて行動してました。
持ち物も、生活も、「親が決めること」だった。
でも今は違う。
子どもは「自分の持ち物」を自覚しはじめ、
それを主張する時期に入っていたのです。
問題は、その変化に親である私自身が気づけていなかったこと。
私はまだ「私が決める」が当然だと思っていたし、
息子は「主張する」意識が育ち始めたのでした。
このすれ違いは、「捨てた・捨てられた」という物理的な問題ではなく、
**親子の役割が変わり始めたことによる“主導権のズレ”**だったのです。
第2章:なぜ親は子どもにしがみついてしまうのか?
頭では「自立してくれて良かった」と思っていても、
子どもとの距離ができてくると、どこかモヤモヤした気持ちになる。
「最近、連絡くれないな」
「私の存在、もう必要ないのかな…」
そんなふうに感じてしまうのは、
実は「しがみつきたい気持ち」が潜んでいるからかもしれません。
親が子どもにしがみついてしまうのは、
多くの場合、自分の人生が空っぽに感じる瞬間に直面するからです。
子育てに多くの時間と愛情を注いできた人ほど、
役割が終わると「自分には何が残るの?」という不安に飲まれてしまう。
たとえば…
- 何かにつけて連絡を取ろうとする
- 進路や仕事に口を出してしまう
- 金銭的に援助しすぎてしまう
それらは「心配しているから」という名目でも、
本当は「関わっていたい」「必要とされたい」という感情の裏返しかもしれません。
大切なのは、その感情を否定せず、自覚することです。
子どもの自立とともに、親自身も“自分の人生を生きる”タイミングに来ているのです。
第3章:「子どもに好かれたい」が、関係を歪める
「嫌われたくない」「ずっと好きでいてほしい」
それは親の自然な感情です。
でも、その思いが強すぎると、親子関係に微妙な歪みが生まれます。
たとえば…
- 叱るべき場面で叱れない
- 頼まれごとを断れない
- 本当は納得していないのに「いいよ」と言ってしまう
こういった行動が続くと、子どもは無意識のうちに
「親は自分の期待に応えてくれる存在」だと認識し、
対等な関係ではなくなっていきます。
“愛されようとする親”は、“導く存在”ではいられない。
子どもにとって必要なのは、
時にNOを言ってくれる大人の存在です。
それこそが、本当に愛のある、信頼される親の姿だと私は思います。
第4章:親が人生を生きる姿を見せることが、最後の子育て
子どもが巣立ったあと、
親は「次に何を生きるのか」が問われます。
子どもが中心だった生活を手放したあと、
空白を感じるのは当然のことです。
でも、そこからどう生きていくか。
それこそが、**親としての最後の役割=“背中を見せること”**ではないでしょうか。
- 理不尽に向き合う姿
- 新しい挑戦をする姿
- 年齢に関係なく人生を楽しむ姿
そういった日常こそが、
「親が親としてどう生きたか」を物語っていくのです。
第5章:巣立った子どもとどう付き合う?距離感と信頼のバランス
子どもが大人になると、親の存在は
「感情」ではなく「現実」で捉えられるようになります。
- 困った時だけ連絡が来る
- 親を“使う”ような言動に見える
- 感謝の言葉がない
そんな時、悲しくなったり、イラッとすることもあるかもしれません。
でも、それは“親子関係が大人の関係に変わった証”でもあるのです。
これからの親子関係に大切なのは、以下の3つです。
- 感情で動かず、条件で考える
- 感謝がなくても与えた自分を認める
- 親も、自分の生活・尊厳を大切にする
子どもとの距離は、「親だから」ではなく、
「自分の心が安定する位置」で決めていい。
あとがき:子育ての終わりとは、親が“自分を生き始めること”
親子は切れない縁でつながっている。
けれど、人生の目的も、ゴールも、歩む道も違うのが当たり前。
どちらかが無理に合わせれば、関係は苦しくなる。
子どもに依存せず、
好かれようと必死にならず、
役割ではなく“自分”を生きていく。
それこそが、
**親がたどり着く“最後の子育て”**なのだと思います。
補足(モデルケースについて)
本記事は以下のような家庭をモデルにしています:
- 子ども中心の生活を長く送ってきた核家族
- 写真フォルダには子どもの成長記録が並び、
- 買い与える・手伝うことが愛情表現だったご家庭
似た状況の方にとって、
この内容が心の切り替えのヒントになれば嬉しいです。
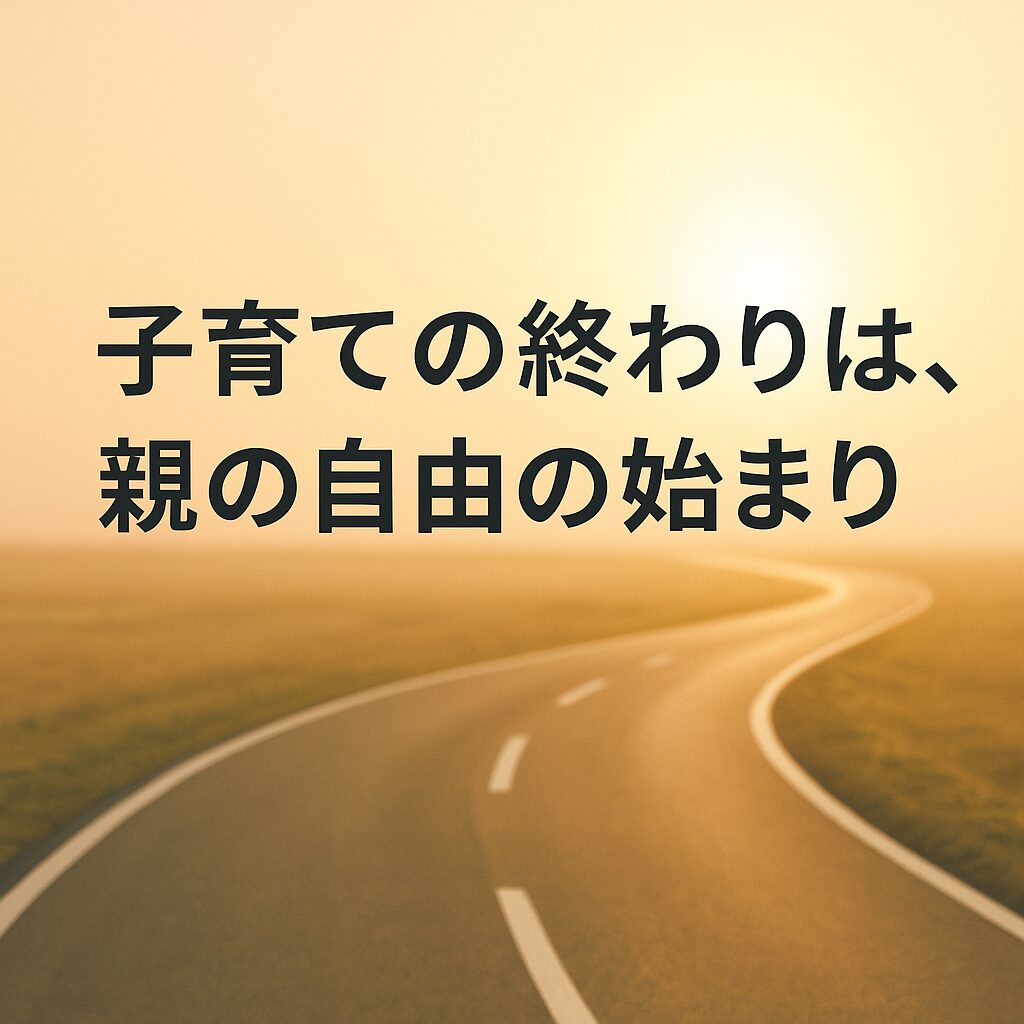
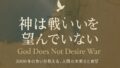

コメント